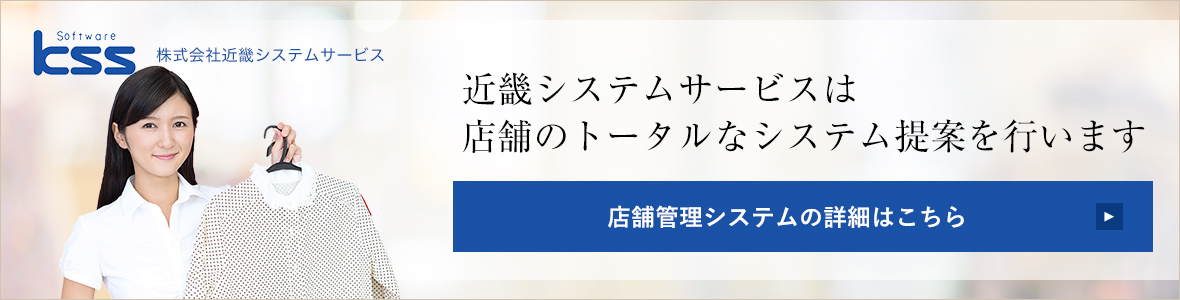小売や飲食、アパレルなどの業種を問わず、店舗を経営するためのファクターになるのが、店舗管理の業務です。
この業務をきちんと行っていないと、店舗の経営が傾くのは火を見るよりも明らかです。
店舗管理はそれだけ重要な店舗管理業務ですが、効率的に店舗を経営したいと考えている事業者の頭を悩ませている課題がいくつかあります。
ここでは、店舗管理業務の内容に触れつつ、どういった課題があるのか、その課題を解決するための手段を見ていきます。
目次
店舗管理とは
店舗管理は事業の持続を左右する重要な業務です。特に複数展開している企業においては、各店舗の状況を本部が適切に把握・管理することが不可欠です。
管理体制が不十分だと、店舗責任者への負担やサービス品質の低下、収益性の悪化などの問題が発生するかもしません。
本部によるマネジメントシステムの構築が、安定した店舗運営の基盤となります。
ここでは店舗管理の概要を詳しく解説します。
店舗管理とは
店舗管理は実店舗の運営において大切な業務です。経営者や店長は日々の売上データを分析して売れ筋商品やピークの時間帯を把握し、効率的な在庫管理や人員配置をおこないます。
また、従業員の勤怠管理を通じて適切なシフト作成や労務管理を実施し、健全な職場環境を整えます。
さらに仕入れ管理によって、取引先との良好な関係維持や価格交渉、納期の管理などを通じて、安定した商品を供給できる体制を確保する業務です。
また、顧客満足度の向上も店舗管理の重要な目的の一つです。接客サービスの質を確保するための従業員教育や、クレーム対応などを通じて、リピーターの確保や新規顧客の開拓を図ります。これらの業務を総合的にマネジメントすることで、店舗の収益性向上と成長を促します。
店舗管理者と店長の違い
店舗管理者は経営戦略の策定や予算管理、業績分析などの経営面を重点的に担当する登録販売者です。複数店舗の統括や本部との連携、収益性の向上施策の立案もおこないます。
一方、店長は現場での業務遂行がメインとなり、従業員の育成やシフト作成、在庫管理、接客サービスの品質管理などを担当します。
日常の店舗運営における業務の決定や問題解決も店長の重要な役割です。
どちらも密に連携し、店舗管理者の経営方針や戦略、そして店長が現場で具体化することで、効果的な店舗運営が実現されます。
主な店舗管理の仕事内容
店舗管理の主な仕事内容は下記のとおりです。
- 売上管理や分析
- 在庫や仕入れ状況の確認
- 従業員が日々業務をこなしているのかのチェック
- 従業員の勤怠管理
- 棚卸などが店舗管理
他にも、店舗の設備維持や備品の購入、システムの導入や利益向上のための施策なども店舗管理業務の一環です。
多店舗展開をしている場合、本部サイドの業務内容としては、店舗ごとの売上や在庫などを管理しつつ、マネジメントをすることが業務内容になります。
店舗サイドは、本部サイドが店舗の状況を把握できるように報告書などを作成することも業務の一環です。
このように店舗管理の業務はさまざまで、やらなければならないことが多いです。
店舗管理業務の課題

店舗を円滑に経営するために行われる店舗管理業務です。しかし、内容はとても幅広く、やらなければならないことが多いため、事業者の頭を悩ませる課題が多々あります。
店舗サイド
まずは、店舗サイドの業務の課題についてです。
主に以下があります。
- 売上の管理・分析
- 在庫の管理
- 従業員の管理
- 本部に報告することが多い
- 店舗内の管理で手がいっぱいになる
それぞれ解説していきます。
売上の管理・分析
売上管理とは、店舗や企業の収益状況を把握・分析し、売上目標の達成を目指す業務のことです。日次・月次の売上データを収集・分析し、商品別・時間帯別の売上傾向を確認します。
売上アップのためには、店舗の現状を踏まえたうえで施策を練る必要があります。
その一環で売上・購買のデータを分析することが多々ありますが、この業務負担は限りなく大きいと言わざるを得ません。
例えば飲食店では、個別で伝票に注文内容を記載し、合計金額だけをレジに打ち込むとなると、営業が終了するまで待ち、伝票とレジ内の金額を照合しながら計算する必要があります。
これを営業終了後に毎日やるとなると、売上管理だけで多くの時間を費やすことになります。
これでは曜日別・商品別の売上分析がままならない状態になり、時間帯別の購買行動を分析できません。
この問題をクリアしない限りは、売上アップのための施策を練るのは難しいと言えます。
また、売上管理に関して詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
>>売上管理とは?管理方法やスムーズにおこなうためのポイントをご紹介
在庫の管理
スムーズな在庫管理は店舗運営の要です。取扱商品が多い場合、各商品の在庫数把握が複雑化し、管理負担を増やすことになりかねません。
在庫の維持には、発注・仕入・棚卸の正確な実行が必要です。特にがあります。
そのため、現状の在庫数の正確な把握と、それに基づく計画的な在庫管理が有効です。
従業員の管理
従業員のシフトや勤怠管理、そして日々の業務をきちんとこなせるように指導するのも、店舗管理業務の1つです。
従業員の管理で事業者の頭を悩ませるのが、他の業務が忙しくて指示が疎かになってしまうことと、従業員の勤怠管理です。
解決策としては小規模な店舗でも勤怠管理アプリを活用することで手作業を削減し、指導する時間の確保が可能です。
なお、従業員の勤怠管理ももちろん必要ですが、スタッフが働きやすいように社内の環境整えるのも業務に含まれます。
スタッフのケアをしっかりおこなえていないとスタッフの離職につながるため、注意しなくてはなりません。
本部に報告することが多い
店舗責任者が直面する本部報告の主な負担は以下のとおりです。
- 日次での売上・客数報告
- 在庫状況の報告
- 従業員の勤怠集計
- クレーム対応の詳細報告
- 販促施策の実施状況
このように、報告しなければならない項目は多岐にわたります。特に手書きでの報告書作成は時間を要し、通常業務を圧迫します。
また、本部からの急な問い合わせや追加報告の要請対応も、スケジュールを乱す要因です。これらの報告業務により、本来注力すべき店舗運営や従業員管理に十分な時間を確保できない状況が生じています。
店舗内の管理で手がいっぱいになる
売上や在庫、従業員の管理など店舗管理業務は多岐にわたり、それだけで責任者のタスクが埋まってしまうケースが往々にしてあります。
そのため、経営改善や売上向上のための戦略的な業務に時間を割けない状況が生まれます。
反対に本部への報告や売上アップの施策を優先してしまうと、他の店舗管理業務が疎かになってしまうので、それこそ経営が傾く原因になりかねません。
店舗管理業務の課題|本部サイド
続いては、本部サイドの課題をご紹介します。
- 店舗ごとの現状が把握できない
- 店舗数が多すぎて、トータルな売上が把握できない
この2つの懸念点を細かく見ていきましょう
店舗ごとの現状が把握できない
多店舗展開をしている場合、本部は店舗ごとの現状(売上・在庫数など)を把握したうえで売上向上のための分析やコンサルティングなど、総合的な管理をする必要があります。
売上データや在庫数値だけでは、店舗の実態を十分に理解できません。接客品質や従業員のモチベーション、店舗の雰囲気、設備の状態など、特に数値化できない要素の把握が難しく、問題が表面化するまで気付けないケースも多発します。
さらに、店舗からの報告内容と実態との違いや、報告タイミングのばらつきにより、適切な経営判断や支援が遅れるケースも存在します。
店舗数が多すぎて、トータルな売上が把握できない
各店舗の立地や客層の違いにより、商品の売れ行きにばらつきが生じることで、情報収集してから分析するまでの作業に時間がかかってしまいます。
また、タイムリーな売上データの集計が正しくできないため、在庫調整や販促施策の全社的な展開が遅れ、その分機会損失や在庫ロスになることもあるでしょう。
さらに、店舗間の売上比較や問題店舗の特定ができず、経営の改善が大きく遅れてしまうかもしれません。
業務をスムーズにするには?
業務を効率化させるためには、マニュアル作成や店舗管理システムの導入がおすすめです。
マニュアル作成で業務の見える化を図る
業務マニュアルとは、日常的な店舗業務の手順や規則を文書化した書類のことです。例えば、開店から閉店までの作業や接客手順、在庫管理方法、緊急時の対応など、業務に必要な情報を体系的にまとめています。
従業員教育の効率化と標準化が実現でき、管理者の指導負担が軽減されます。また、業務の変化を防ぎ、人材の入れ替わりにも対応できます。
さらに、作業手順が明確になることで、スタッフの人的ミスの防止やサービス品質の均一化が図れるでしょう。
緊急時や不測の事態でも、マニュアルを参照することで適切な対応が可能となり、店舗運営の安定性が向上します。
店舗管理システムを導入する
店舗管理システムとは、売上管理や在庫管理、勤怠管理、顧客管理などの店舗運営業務をデジタル化し、一元管理するためのツールを指します。
店舗管理システムを採用することで本部への報告業務が自動化され、手作業による負担が大幅に軽減できます。リアルタイムでの売上・在庫状況の把握が可能となり、迅速な意思決定が可能です。
さらに複数店舗のデータを統合分析でき、効果的な経営戦略の立案に活用できるのがメリットです。
また、従業員の勤怠管理も正確かつ効率的となり、給与計算の手間も削減されます。店舗管理を一括でまとめられるため、店舗責任者は本来の店舗運営業務に注力できるようになります。
店舗管理システムに関して詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。
店舗管理システムの選び方
店舗管理システムを導入しようと思っている方は、コスト以外にも注意したいポイントがあります。ここでは3つの選び方を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
- 自社の業務内容に合っているか
- モバイル対応しているか
- 店舗数の増減に対応できるか
自社の業務内容に合っているか
店舗管理システムを採用する際は、業種の特性に応じた機能を選ぶことが大切です。
例えば、アパレル店では商品の色・サイズ別での在庫管理、飲食店では食材・消費期限・座席予約管理が必須です。
自社の業務フローに合わないシステムを導入すると、作業効率が低下するだけではなく、従業員の研修に時間がかかります。そのため、現場の具体的なニーズを把握し、自社に適したシステムを探すことがスムーズな運営に役立ちます。
モバイル対応しているか
モバイル対応の店舗管理システムは、現場での迅速な情報共有と業務効率化を実現します。スマートフォンやタブレットで店舗状況の記録や在庫確認など、スタッフ同士がリアルタイムでおこなえます。
特に人手不足の店舗では、移動時間の削減や複数業務の同時処理が可能となり、作業効率が向上します。導入時は現場のデバイス使用状況や通信環境を考慮し、操作性のよいシステムを選択するのがおすすめです。
店舗数の増減に対応できるか
クラウド型の店舗管理システムは、店舗数の増減に応じて利用料金を調整できる柔軟性が特徴です。
1店舗単位での契約が可能なため、事業規模の拡大縮小に合わせた対応ができます。ただし、店舗数増加にともなうデータ量の増大に対応できる処理能力の確認が重要です。
大量データの処理速度低下やシステム障害を防ぐため、導入前にシステムの性能要件を慎重に検討する必要があります。
また、近畿システムサービスでは、導入・運用方法を選べる便利な店舗管理システムをご提供しています。気になる方は下記の記事をご覧ください。
店舗管理システムを導入すれば課題を解決できる
 店舗サイドと本部サイド、双方で抱える店舗管理業務の問題点や課題を解決する方法としては、店舗管理システムを導入することが挙げられます。
店舗サイドと本部サイド、双方で抱える店舗管理業務の問題点や課題を解決する方法としては、店舗管理システムを導入することが挙げられます。
店舗管理システムは、お伝えしたような課題を解決できるような機能を豊富に備えています。
例えば、売上管理や在庫管理、勤怠管理や経費管理など、店舗の経営に欠かせない機能を備えているだけでなく、店舗ごとの売上管理などができる本部管理機能も備えています。
店舗管理におけるありとあらゆる課題を解決できるので、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。