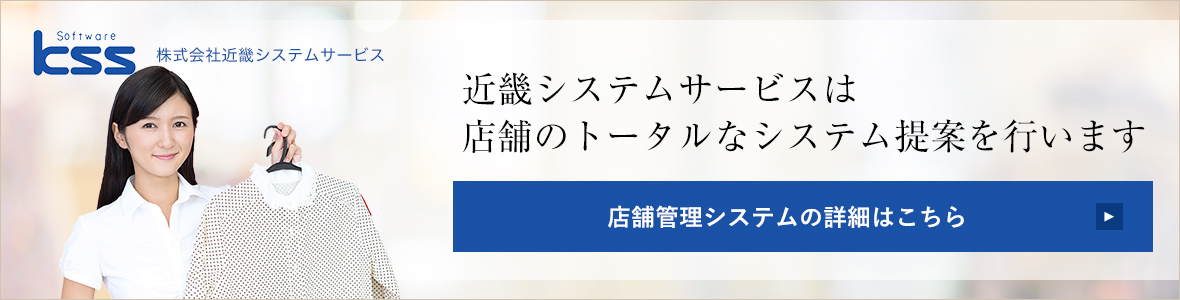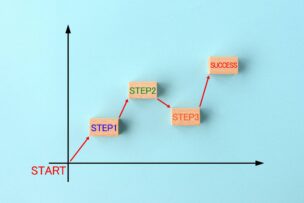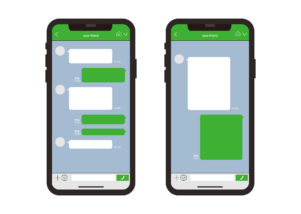企業の経営において、在庫管理の棚卸し業務は、自社の利益を把握するために欠かせない業務です。棚卸しは、経営判断の基盤となるだけでなく、店舗に滞留するコストの削減や業務効率の向上にもつながります。
しかし、「在庫が合わない」「適正在庫がわからない」などの悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。棚卸しをすることで、商品の過不足を防ぎ、売り上げやコストの管理を適正に行えます。
この記事では、棚卸しの目的や具体的なやり方をわかりやすく解説します。
また、決算時や確定申告の際にも正確なデータが求められるため、正しい方法とタイミングで実施するポイントもご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
目次
棚卸しとは?

棚卸しは企業にとって重要な業務ですが、実際にどのような作業を行うのかをご紹介します。
棚卸しとは在庫数を確認すること
棚卸しとは、企業が保有する商品の在庫資産を実際に数え、帳簿上の記録と照合する業務です。棚卸し作業は通常の業務を一時中断して、社内全体で取り組む必要があり、多くのスタッフが時間を要します。
企業は、決算時に正確な経営成績(決算書)を税務署や都道府県税事務所、市役所に報告する義務があります。利益を算出するためには、実在庫と理論在庫数の差異を明らかにし、原因の特定が不可欠です。
きちんと在庫管理がなされていないと、棚卸し作業自体が長期化し、企業活動に支障をきたす恐れがあります。
また、棚卸しの差異に関する対処法を知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。
棚卸しの目的
棚卸しを行う主な目的は以下の通りです。
| 目的 | 内容 |
| 在庫管理の適正確認 | ・実在庫と帳簿上の数値を照合し、在庫管理が正しく行われているかを検証する
・帳簿に差異があるときは入力ミス・紛失の可能性がある |
| 事業利益の正確な把握 | ・実際の在庫価値を計算することで、利益状況を明らかにする
・売上総利益に影響する |
| 販売機会損失の特定 | ・品切れや在庫不足の状況を把握することで、売上機会の損失を防止するための情報を得られる |
| 在庫品質の確認 | ・商品の劣化や破損などの状態を確認し、不良在庫の発見と対策につなげる |
棚卸しは在庫状況を確認し、事業の利益を把握するために重要な作業です。実際の在庫と帳簿の差異を確認し、販売機会の損失を防ぐだけでなく、品質や状態をチェックして適切な管理を行う目的もあります。
なお、売上総利益は売上高から売上原価を引いて計算されますが、この売上原価の算出には期首在庫と期末在庫が必要です。棚卸しによって適切な在庫金額が把握できれば、売上原価が算出でき、結果として適正な売上総利益を算定できます。
棚卸しの目的に関して下記のコラムでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
棚卸しを行うタイミング
棚卸しを行う時期には、法的な期限や厳格なルールは設けられていませんが、一般的には年度初めの「期首」と年度末の「期末」に行われます。3月決算企業では、期末や中間期末に棚卸しを行っています。
特に重要なのは、利益計算に不可欠な決算前の期末棚卸しです。期首と期末の両時点で棚卸しを実施することで、年間を通した在庫変動を正確に把握でき、より精度の高い会計処理が可能となります。
業種によって異なりますが、棚卸しの頻度は最低でも年1回がおすすめです。特に飲食業や小売業のような、在庫切れが事業の継続に直接影響する業種の場合、月次で棚卸しを実施するケースがほとんどです。普段から定期的に行うことにより、常に最新の在庫状況を把握でき、的確な発注計画や在庫管理ができるようになります。
棚卸しの種類

棚卸しする方法は、主にリスト方式とタグ方式の2種類です。ここではそれぞれの特徴を解説します。
リスト方式
リスト方式とは、在庫を目視で数えながら、自社で作成した在庫管理表の数量と実際の在庫数を照合する実地棚卸しの一つです。事前に作成したリストを基にチェックするため、在庫の確認がスムーズに進みやすいのが特徴です。
しかし、リスト自体に誤りがあると、カウント漏れや数量のズレが発生しやすいというデメリットもあります。また、手作業での確認が多いため、人為的ミスが起こる可能性もあります。正確な在庫管理のためには、定期的なリストの更新やダブルチェックが必要です。
タグ方式
タグ方式は、担当者が商品を一つひとつ確認しながら荷札(タグ)に名前と数量を記載し、現物に貼り付けることで実在庫を把握する方法です。
あらかじめ実際の倉庫にある在庫数を確認してから在庫管理表の理論値と照合するため、記録間違いや計上漏れのリスクを軽減できる点がメリットです。
しかし、タグ方式は商品ごとに荷札を作成し記入する作業が生じてしまい、多くの時間と労力を必要とするデメリットも存在します。
正確な在庫管理を実現する上では効果的な手法ですが、作業効率性とのバランスを考えることが大切です。
棚卸しの評価方法

棚卸しにおける評価法は主に2つです。どちらを選択するかは、事前にどのような内容なのかを知っておくことが大切です。
原価法
原価法とは、棚卸し資産の評価方法の一つで、商品や原材料などの在庫を仕入れ時の原価(取得原価)に基づいて評価する手法です。取得価額を計算するためには、下記の方法があります。
- 個別法
- 先入先出法
- 総平均法
- 売価還元法
- 移動平均法
- 最終仕入原価法
在庫の取得にかかったコストを基準に評価を行うため、計算が比較的単純なのがメリットです。
特に、財務諸表作成では、客観的な数値に基づく安定した評価が可能となり、会計処理を一貫して保てます。ただし、時間の経過による在庫の経年劣化や市場価格の下落といった要因を自動的に反映できない点がデメリットとして挙げられます。
特に市場の変動が激しい業種や、劣化しやすい商品を扱う企業は、原価法のみに依存すると財務状況の正確な把握が困難になる可能性があります。
低価法
低価法は、企業が保有する棚卸資産の評価を行うための会計手法です。資産価値が当初の仕入れ時より下落している状況を財務諸表に反映させられます。
原価法で算出した金額と期末時点の時価を比較し、より低いほうの価額で資産評価を行います。これにより、市場価値の変動や商品の劣化などによる資産価値の減少について会計上で正確な表現が可能です。
低価法を適用した場合には、翌期首に振り戻し処理が必要です。この振り戻し(再振替)は、当期に資産価値の減少として計上した金額を翌期の期首に調整します。
参照:国税庁|棚卸資産の評価に関する会計基準と法人税法の調整の方向性
在庫管理における棚卸しの手順

棚卸し作業を行うには、まず表の作成(棚卸表)が必要です。棚卸表とは、商品名や数量、状態など商品情報を整理した一覧表を指し、エクセルのような表計算ソフトの活用で効率的に作成できます。
一度テンプレートとして保存しておくことで、定期的な棚卸し作業の効率化が図れます。棚卸しは、以下の手順で行うのがおすすめです。
- 事前に作成した棚卸表をもとに現場で棚卸しを行う
- 在庫として保有している原材料や商品の個数・重量を正確に計測する
- 測定結果を棚卸表に漏れなく記録する
- 棚卸表のデータを分析する
- 欠品にならず、ロスも発生しない最小限の在庫数を適正在庫として把握する
- 分析結果を今後の仕入れ計画や在庫管理に活用する
棚卸しによる分析結果は、今後の仕入れや生産計画の指標となり、経営効率の向上に直結します。
また、棚卸しの効率化を目指す方は下記の記事も併せてご覧ください。
棚卸しをスムーズに行うコツ

会社で棚卸しを行う際は、ある程度ルールを決めておくことが大切です。ここでは棚卸しをスムーズに行うポイントとともに、注意点も併せてご紹介します。
棚卸しの責任者を決めておく
責任者を決めることにより作業全体の統制が取れ、手順のマニュアル化と品質管理が自然とできるようになります。また、不明点や問題が発生した際の判断基準が明確になり、迅速な対応が可能です。
さらに、複数の部署や担当者が関わる場合でも、責任者同士で連携がスムーズになり、作業効率が向上します。最終的なデータの精度と信頼性を担保するためにも、専門知識と権限を持つ責任者を決めておくと良いでしょう。
普段から整理整頓を心がける
正確な棚卸し作業を遂行するためには、「ロケーション管理」がおすすめです。倉庫や保管エリアを区分け・番号付けし、各商品の保管位置を管理します。在庫の場所が一目で把握でき、棚卸しする際に商品を探す時間が短縮されます。
また、整理されていれば誤ったカウントや商品を見落してしまうこともなくなり、棚卸し精度の向上につながります。
書類を保存しておく
棚卸し作業は、申告内容の正確性を担保する基盤となります。法人だけではなく個人事業主も、1月から12月までの事業年度の正確な利益を算出し申告するために、棚卸資産の評価が必要です。
棚卸表は税務調査が実施された際に、申告した税額計算の根拠として提示を求められる証拠資料です。
なお、税法上の要件として、青色申告では7年間、白色申告では5年間にわたる関連書類の保存が義務付けられているため、必ず保管しておきましょう。
システムを利用する
現在多くの企業では、在庫管理に計算ツールを利用していますが、この方法では人為的なデータ入力ミス、関数設定の誤り、ファイル保存の問題など、さまざまなエラーリスクが発生します。
小規模な場合でも積み重なれば、会計上の問題や在庫不足による機会損失につながりかねません。そこでバーコードやQRコードを活用した専用の在庫管理システムの導入で、これらの課題を解決できます。
例えば、商品の入荷や出荷時に自動的にデータが記録され、人為的ミスを削減できます。また、在庫情報がリアルタイムで更新されるのも大きな利点です。さらに、一元管理されたデータベースにより、複数の場所や部署間での情報共有がスムーズになり、企業全体の在庫最適化に役立ちます。
また、店舗管理システムを導入するメリットやデメリット、選び方を詳しく知りたい方は、下記のコラムもご覧ください。
>>店舗管理システムとは?機能や業種別の詳細・おすすめの選び方を解説
まとめ
棚卸しは、企業の在庫資産を実地で確認し、帳簿上の数値と合わせる大切な業務です。棚卸しは月に1度行うのが理想ですが、企業によって人員不足や業務過多などの理由で、きちんと行えないこともあるでしょう。
近畿システムサービスでは、店舗管理システムを提供しており、棚卸し業務と効率化と改善をサポートいたします。店舗ごとに原価・売価を個別設定でき、各店舗の立地条件や客層に合わせた価格戦略を実現できます。
また、売上帳票出力時には、税抜売上金額と税込売上金額の両方を表示できるため、会計処理や税務申告の際に必要なデータを即座に確認できます。
当社の店舗管理システムが気になる方は、お気軽にご相談ください。