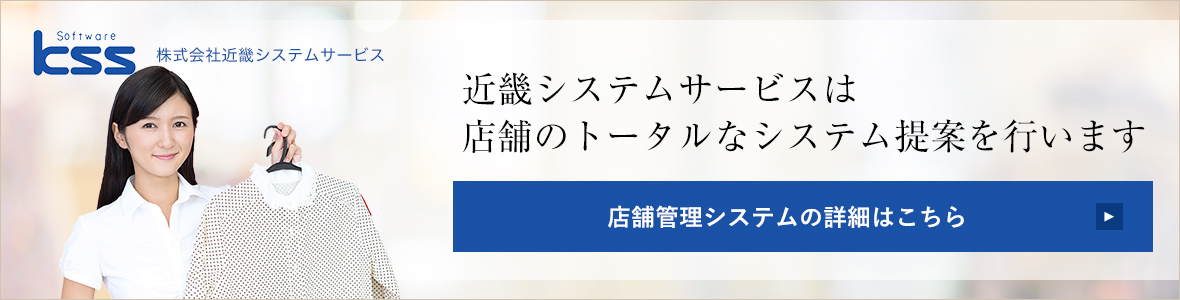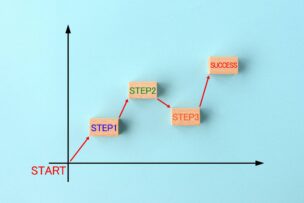個人で育てた農産物を販売したい場合、許可や届け出は必要になるのでしょうか。
この記事では、農産物の販売に必要な許可について解説します。また、委託販売や買取販売などの販売方法、道の駅やネット販売といった農産物の主な販売ルートについてもまとめました。
目次
農産物の販売に許可は必要?
自分で栽培した野菜や果物などの農産物をそのまま販売する場合、特別な許可を得る必要はありません。自分で栽培した農産物の収穫・販売は営業に含まれないことが食品衛生法によって明確にされています。
| 食品衛生法第4条第7項の規定により、農業及び水産業における食品の採取業は、営業に含まないとしており、HACCP に沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。 |
ただし、場合によっては食品営業許可や食品営業届出が必要になることがあります。許可が必要になるケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。
許可が必要なケース①他農家の農産物を販売する場合
他の人が栽培した農産物を販売したい場合、管轄の保健所に「野菜果物販売業」の届け出が必要になります。届け出は無料で、オンラインでも申請可能です。
野菜果物販売業の届け出をする際、食品衛生責任者を明記する欄があるため、必然的に「食品衛生責任者」の資格も必須となります。
許可が必要なケース②農産物加工品を販売する場合
野菜や果物を調理して作った「農産物加工品」を販売する場合、管轄の保健所に「営業許可」を申請する必要があります。また、「食品衛生責任者」も一人以上必要です。
ジャムやドレッシングなどの長期保存が可能な商品を販売する場合は、「密封包装食品製造業」の届け出が必要になることがあります。
どの許可や届け出が必要かわからない場合は、管轄の保健所に相談してみましょう。
許可が必要なケース③農産物を調理して販売する場合
農産物をその場で調理して販売する場合、「飲食店営業」の申請が必要になります。
具体的には、フードトラックやキッチンカーで野菜を販売しながら、スイーツや飲み物を販売する場合などには飲食店営業の許可が必要です。
また、飲食店営業の許可を得るには「食品衛生責任者」の資格も必要です。
農産物の販売にはどのような方法があるのか
農産物を販売する方法には、「直売」「委託販売」「買取販売」の3つがあります。
直売
「直売」は、農産物の作り手が直接販売する方式です。自宅や農場の近くに販売所を設けるケースが一般的で、地域の人からの購入がほとんどとなります。
近年では「ネット販売」も普及しつつある直売での販売方法で、認知度を上げるためにはSNSの活用や販売ページの工夫が必要になります。
委託販売
「委託販売」では、商品が売れるごとに販売手数料を支払うことで農産物の販売を委託できます。手数料の相場は15%前後と比較的低く、さらに手数料が発生するのは売れた分だけという点は、委託販売を選ぶ上での大きなメリットです。
ただし、売れなかった分はもちろん売り上げにならないため、売り上げが保証されない点はデメリットとなります。
委託販売は、主に道の駅や農産物直売所で取り入れられています。
買取販売
「買取販売」では、飲食店や加工業者がまとまった数の農産物を買い取ってくれます。買い取られた後の農産物は、商品となって販売されることになります。
飲食店や加工業者との契約が結べれば安定して売り上げが立つという大きなメリットがありますが、契約を取るには他の農産物との差別化や魅力のアピールが重要になります。
農産物の販売ルートは主に6つ
農産物が消費者の手に渡るまでの販売ルートには、主に次の6つがあります。
- 農協(JA)
- 道の駅・農産物直売所
- 無人販売
- 個人直売所
- 移動販売
- ネット販売
農協(JA)

農産物のもっとも一般的な販売ルートは、農協(JA・農業協同組合)での販売です。
農協へ出荷するには1,000〜10,000円の出資金を支払い、農協に加入する必要があります。販売の方式は委託となり、価格の決定は農協側が行います。
農協へ加入する以外に必要な許可や届け出はありません。
農協で農産物を販売するメリット・デメリット
小規模の出荷先の場合、農作物の価格が暴落していると買い取りを拒否されることがありますが、農協では基本的に規格を満たしていれば時期にかかわらず買い取りしてくれます。また、加入者が多いことで安定した量を出荷できるため、比較的高価格での農作物の販売が可能です。
このように農作物を安定して出荷し、安定して売り上げを立てられる点が農協の大きなメリットです。
ただし、荷造り運賃や段ボール代などの販売手数料が発生し、割合は25〜30%と割高になるため、販売手数料を抑えて少しでも売り上げを増やしたい方にとってはデメリットとなるでしょう。
道の駅・農産物直売所

道の駅や農産物直売所での販売も、一般的な農産物の販売ルートです。地元の消費者から観光客まで幅広い客層を取り込めるのが特徴です。
規模はさまざまで、季節やその土地の名物であるかどうかなどによっても売り上げは左右されるでしょう。
販売は、委託方式で行われ、必要な許可や届け出はありません。
道の駅・農産物直売所で農産物を販売するメリット・デメリット
道の駅や農産物直売所で販売する農産物は、価格を自分で決められることが大きなメリットです。その場所での需要が高い場合は価格を高めに設定しても売れるため、売り上げを立てやすくなります。
その分競争率が高く、売れ残った農産物は引き取らなければならないというデメリットもあります。
無人販売

自身が所有する土地の一角を利用し、その名の通り無人で販売します。直売のため、許可や届け出の必要はありませんが、農産物加工品を取り扱う場合は営業許可が必要になります。
無人販売で農産物を販売するメリット・デメリット
無人販売は、売り上げの全てを収入にできることが大きなメリットです。また、商品を並べる・補充する・売り上げを確認するという3つのステップだけで営業が成り立つため、手軽に始められるのもポイント。
デメリットとしては、代金を払わずに農産物を持っていってしまう人がいるなどのリスクがあるほか、立地や天気によって売り上げが大きく左右されてしまうことが挙げられます。
個人直売所

個人直売所として、自身が所有する土地の敷地内で直売所を開いて販売する方法もあります。小規模な台や小屋を設置して販売しているケースが多く見られます。
許可や届け出は基本的に不要ですが、農産物加工品を取り扱う場合は営業許可が必要になります。
個人直売所で農産物を販売するメリット・デメリット
個人直売所では、無人販売と同様に売り上げが全て収入になることがメリットです。販売価格も自由に決めることができるほか、品揃えや売り方、品質なども独自に工夫できる自由度の高さもメリットであると言えます。
その分、集客ができるかどうかも自分次第になるため、はじめのうちは売り上げを立てるのに苦労する可能性があります。
移動販売

軽トラやキッチンカーなどで、店舗を持たずにさまざまな場所で農産物を直売するのが移動販売です。
農産物加工品を取り扱う場合は営業許可が必要になります。また、公道で販売する場合は市区町村で道路の使用許可を取る必要があります。
移動販売で農産物を販売するメリット・デメリット
販売所を持たないため、集客が見込める場所に自らおもむいて販売ができるのが移動販売のメリットです。また、車があれば販売できるので、初期費用を比較的抑えられます。
ただし、移動販売の特性上、常連客やリピーターを獲得しづらいというデメリットがあります。
ネット販売

農産物の新しい販売方法として普及しているのが「ネット販売」です。フリマアプリやネットショップで直売する方法と、大手宅配チェーンに出荷する方法の2つが主流となっています。
どちらの場合も、農産物加工品を販売しない場合は許可や届け出の必要はありません。
大手宅配チェーンへの販売方法は委託・買い取りのどちらもあるほか、利用料や手数料なども異なるため、利益を得られるように適切な方法をじっくり見極めましょう。
ネット販売で農産物を販売するメリット・デメリット
個人でネット販売をする場合、SNSなどで商品の魅力をうまくアピールして知名度を上げることができれば、直売ながらも全国から注文を受けることができるようになり、売り上げも大きくアップします。
ただしマーケティングがうまくいかない場合は売り上げを見込めない点はデメリットとして挙げられるでしょう。
大手宅配チェーンへの出荷では、農協や道の駅などへの委託販売と大きくシステムは変わりません。集客に注力する必要がないというメリットがありますが、手数料がかかるため、個人でのネット販売に比べると収入は低くなります。
農産物を販売する際に注意すべきポイント
農産物を販売する際に注意したいポイントとして、「有機野菜」「オーガニック」などの表記についてです。
販売する農産物に「有機」「オーガニック」などと表記をするには、「有機JASマーク」という農林水産省の認証が必要になります。これは営業許可などが必要のない直売の場合でも当てはまり、認証なしで表記している場合は法律違反となってしまうため、注意が必要です。
「特別栽培」の表記も同様に認証が必要になります。
まとめ
多種多様な農産物の販売方法の中でどれが適しているかわからない、という場合は、比較的すぐに取り組みやすいと感じるものから始めてみるのがおすすめです。
利益を出せることはもちろん、農産物の魅力やこだわりを消費者に十分に伝えられる方法を選べるよう、積極的に情報を集めてみるとよいでしょう。
近畿システムサービスでは、野菜や果物の在庫・売上管理ができる”店舗管理システム”を提供しています。煩雑になりがちな出荷状況もシステムの導入により一目で分かるようになるなど、さまざまな業務の効率化を図ることができます。
導入を検討している方はぜひお気軽にお問い合わせください。